施策関連資料REPORT
評価・研究
2019/07/04
【レポート(前編)】総合就業支援拠点「OSAKAしごとフィールド」インタビュー
大阪市内中心部。オフィスビルが立ち並ぶ北浜、土佐堀通り沿いにあるビル。
絶え間なく人が横切るエントランスを抜け、エレベーターで2階に上がると驚くほど明るい空間が待っている。
大阪府が設置する総合就業支援拠点、「OSAKAしごとフィールド」だ。

<OSAKAしごとフィールドを運営するメンバー(一部)>
OSAKAしごとフィールド(以下、OSFと略記)が前身となる施設から名称を変えオープンしたのは2013年のこと。2017年度からはNPO法人HELLOlifeを代表構成員とする共同事業体が運営を受託し、内観、内容共に大きく変化した。本レポートでは、2017年から2年間でOSFがどのように変化したか、その内容を追っていきたい。
(1)OSFとは
OSFは、大阪府が設置する公的な就業支援拠点である。キャッチフレーズは「企業と人が出会う場所」。年齢・状況を問わず「働きたい」と考える全ての人を支えると共に、大阪府内の中小企業の採用支援も行う。
OSFが求職者向けに取り組むメニューは以下の6つ。若者、女性、中高年齢者、障がい者など幅広い層を対象に就職支援を行っているのが特徴である。
01.キャリアカウンセリング
02.セミナー・企業面接会
03.履歴書等の書類添削、面接特訓
04.求人検索・職業相談・紹介
05.パソコンや作業スペースの利用
06.保育所探し・一時保育サービス
企業に対する支援として取り組むメニューは主に以下の7つ。ターゲットは、人材確保に課題を抱える大阪府内の中小企業である。府内では、特に製造・運輸・建設といった業界における人材不足が深刻だ。OSAKAしごとフィールドは、こうした中小企業を対象に、職場環境の改善や情報発信の支援を行うことで「働き方改革」を進め、人材紹介と定着を支援している。
01.人材確保に関する相談窓口
02.企業向け採用支援セミナー・イベント
03.マッチング支援(企業交流会・企業説明会)
04.定着支援セミナー・研修
05.人材紹介支援
06.企業主導型保育事業相談窓口
07.その他のサポート
■職場体験コーディネート
■障がい者雇用
(2)2年間で生まれた変化
運営体制の変更から2年。OSFにはどのような変化が生まれただろうか。
ここでは次の2点を特徴として挙げたい。
1)リノベーションによる空間の刷新
一つ目の変化は、リノベーションによって、空間的に明るい場として刷新されたことである。
OSFに入ってまず驚くのは、施設内が明るく、開放的なことだ。一般的な公的施設とは異なり、木材を使用して作られたテーブルや椅子と芝生で柔らかな空間になっている。

<PCテーブルや、仕切りまで木材を使用している>
エレベーターを降りるとすぐ、目に入るのは黄色い屋根のかかった受付ブース。ブース内には常時、係が在中していて、来館者と言葉を交わしている。
デスクの上にはレインボーフラッグと、同じくレインボーカラーのクマのぬいぐるみが顔を覗かせている。OSFがLGBTsの方への就職支援も積極的に行っていることの現れだ。
空間の真ん中に置かれた人工芝のモニュメントはベンチ替わりにもなっており、時には子どもが遊ぶ姿もみられる。

<テーブルの上に置かれているレインボーの人形>

<OSFの入り口付近に設置されている芝生の山>
入り口の脇の掲示板には、ずらりとチラシが並べられている。パソコンスキル講座、しごと発見カフェ、業界理解セミナー…。その多くが府内近郊の就職関連イベントだ。
その先には、業界研究用のブースが設けられている。特に運輸、製造、建設といった、業界未経験者ではなかなかイメージしにくい業界を選び、実際の仕事道具なども展示しながら、来館者への訴求力を高めている。


<セミナーの情報が掲示されているブース>

<製造・建設・運輸の3業種の魅力を発信するブース>
2)コンテンツの豊かさ、ユニークさ
二つ目の変化が、提供されるコンテンツが充実したことである。
例えば、だれもが通え、就職活動や働く上で役立つことが学べる「はたらく学校」。
通常、就職相談や就業支援というと、「就職すること」がゴールになりがちだ。しかし「はたらく学校」の目標は「社会で活躍するために必要な力を身に着け、活き活きと働き続けている自分を作り出す」こと。「学校」という言葉通り、国語、算数、理科、社会….といったユニークな切り口から、「はたらく」を考える機会が提供されている。
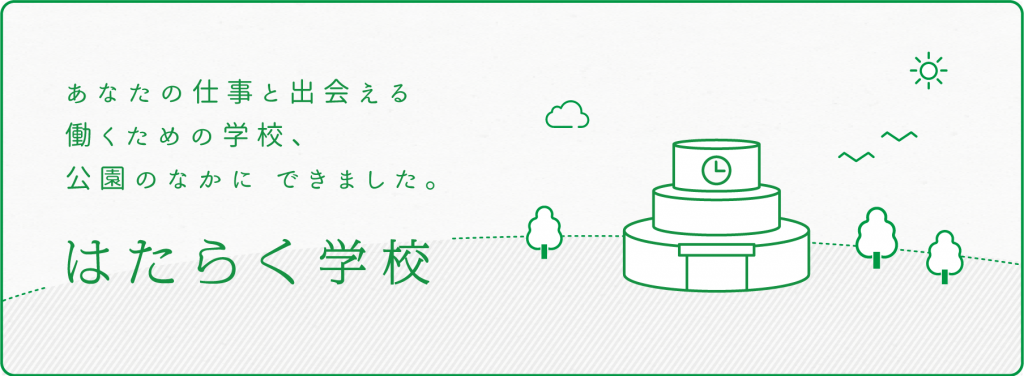

<「はたらく学校」ではユニークなセミナーに取り組んでいる>
2018年2月には、より幅広い層にOSFを知ってもらい、活用の機会を見出して貰うことを目指して、「はたらく学校文化祭」を開催した。こちらはメイクレッスン、料理教室、ライフプラン講座、フリーマーケットなど、楽しみながら気軽に参加できるコンテンツが中心だ。このように、気軽に通えて、仲間と出会い、就職へと旅立つ。そんな「働く」を切り口にした「学校」の運営が目指されている。

<「はたらく学校文化祭」でのフリーマッケットの様子>
また2018年8月には、「就活ビアガーデン」を開催。これまでの「合同企業説明会」のイメージを一新し、素顔で話せる場づくりを行うことを目指した。会場には関西近郊の中小企業40社が出展し、336人が来場するイベントとなった。「就活ビアガーデン」当日のマッチングだけではなく、事前セミナーやアフターフォローにも取り組んだ。

<お酒を片手に企業と求職者が出会える「就活ビアガーデン」の様子>
ほかにも、2017年秋に開催された「LGBT100人会議」など、ユニークなコンテンツが次々と展開されている。
公的な就業支援施設での支援内容というと、ひとりもくもくと備え付けのパソコン画面に向かう、あるいはブースに区切られた面談ルームでカウンセラーと話し合う、といったイメージが強い。
しかしここでの取組みは、そうした個別相談や求職情報の検索、紹介にとどまらない。
働くことに悩んだら、仕事と人生に迷ったら、誰もが立ち寄れる場所。リラックスして自分が求める働き方を探求することが出来る、オープンな公園のような場所。仲間と出会い、働く意味を再考できる場所。そんな場の運営が目指されている。
ではこうした変化はどのように生まれていったのか。
運営側であるハローライフスタッフに聞いた。
(後編はこちら)
(書き手:水谷衣里 /NPO法人HELLOlife参与、株式会社 風とつばさ 代表取締役)